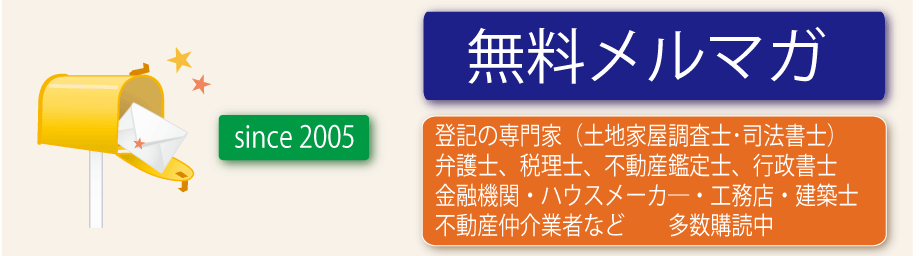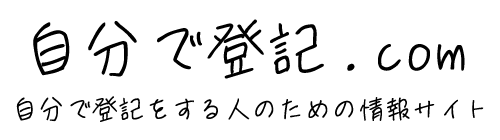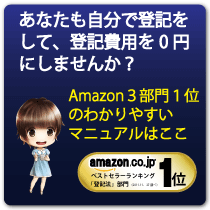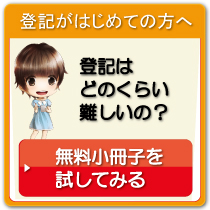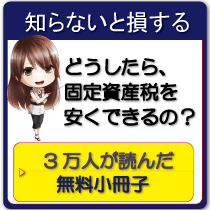自分の土地にあった古い建物を壊して住宅ローンを使って一戸建てを新築
自分の土地にあった古い建物を壊して住宅ローンを使って一戸建てを新築
今回は前回の続きで、どんな登記をすればいいのかというお話です。
下記の場合にどのような登記をする必要があるのかを説明しますね。
わかりやすいように、簡単に書きます。
・自分の土地にあった古い建物を壊して住宅ローンを使って一戸建てを新築
このケースは、住宅ローンを使っての建替えのケースです。
流れとしてはこんなふうになります
1:古い建物を壊します。
2:新しい建物を建てます
3:新しい建物が完成しました
4:住宅ローンを使いお金を借り、建築を依頼した会社に建築費用を払います
まず、1で古い建物を壊しますので、この古い建物が登記された建物であれば、「建物滅失登記」をします。
次に、3で建物が完成したので「建物表題登記」と「所有権保存登記」の順で登記をします。
最後に4で、住宅ローンで建物と土地を担保にしてお金を借りるので、「抵当権設定登記」をします。
これで、終わりです。
このケースでは、
「建物滅失登記」
「建物表題登記」
「所有権保存登記」
「抵当権設定登記」
の順で登記をします。
専門家が登記をする際は、
「建物滅失登記」と「建物表題登記」を土地家屋調査士が建物が完成した際に同時に登記をしますが、自分で登記をする
場合は、建物を壊した時に「建物滅失登記」をして、建物が完成した時に、「建物表題登記」をした方が時間的に余裕が
できるのでその都度登記をすることをお勧めします。
次に、
「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」は司法書士が、お金を借りる時に行うのが一般的です。
自分で登記をする場合は、「抵当権設定登記」を自分ですることをお金を貸してくれる金融機関が嫌がり書類を渡してくれ
ないケースが多いです。
「抵当権設定登記」を自分でやる場合は、司法書士がやるように「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」を一度に行え
ばいいですが、金融機関が嫌がる場合は、「建物表題登記」が終ったらすぐに「所有権保存登記」をしてから、「抵当権設
定登記」を司法書士に任せるのが無難でしょう。
司法書士に任せる場合は、司法書士をネットなどで探して報酬の安い司法書士にお願いすることをお勧めします。
少し難しかったかも知れませんが、これからいくつかのケースを読んでいただければ、こういう時は、この登記をすればいいということが分かるようになります。
次回は、下記のケースについてお話をしますね。
・自分の土地にあった古い建物を壊して、現金で一戸建てを新築
今日も読んでいただきありがとうございました。
最新情報を確実に受け取れます!
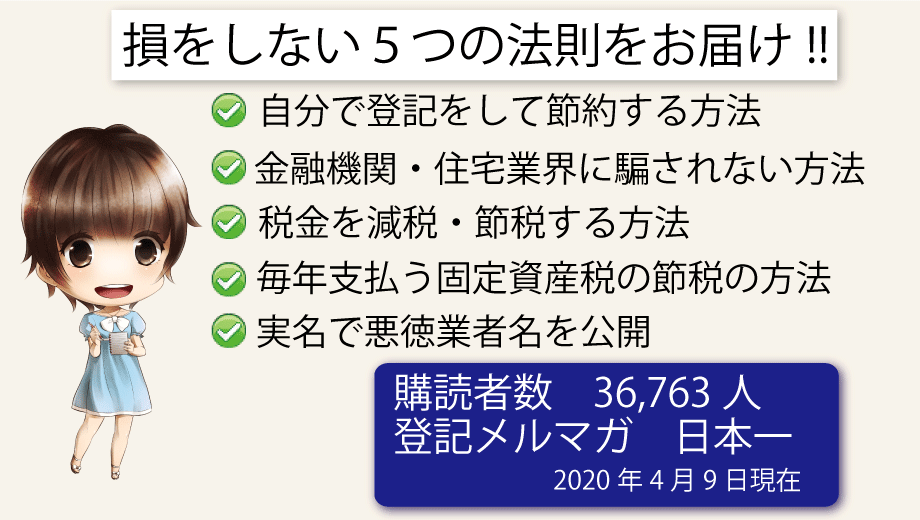
 麻美
麻美日本登記研究会は、あなたへ真実を伝えることを使命と考えています。
でも、ホームページに裏情報や実名などの情報を掲載すると日本登記研究会は営業妨害や名誉毀損などで損害賠償請求をされる可能性があるの。ホームページに掲載された情報は誰もが、いつでも読め、公開されているから。
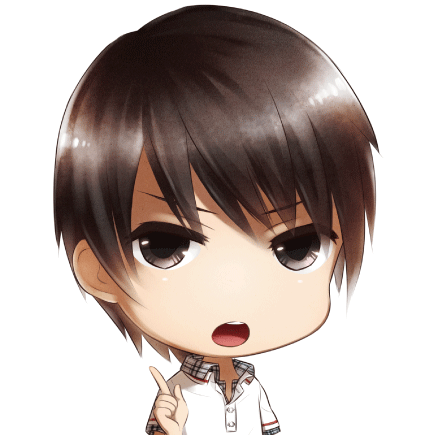 芳樹
芳樹そこで、ホームページに掲載しにくい情報は、日本登記研究会が発行する『メルマガ(メールマガジン)』にて個別に情報を届けています。
このメルマガの読者は3万人を超え、登記に関するメルマガでは日本一です。
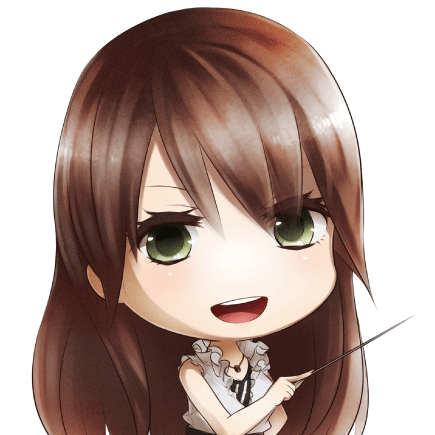 香苗
香苗なお、これまでに無料小冊子を受け取った場合は、既に読者登録されいますので、新たに登録する必要はありません。
 麻美
麻美無料の『メルマガ(メールマガジン)』を読まれますか?
下記の□の箇所に『あなたのメールアドレス』を入力し登録ボタンをクリックしてください。
これだけで登録完了です。登録完了後10分以内に、あなたへ『メルマガ(メールマガジン)』を送信します。
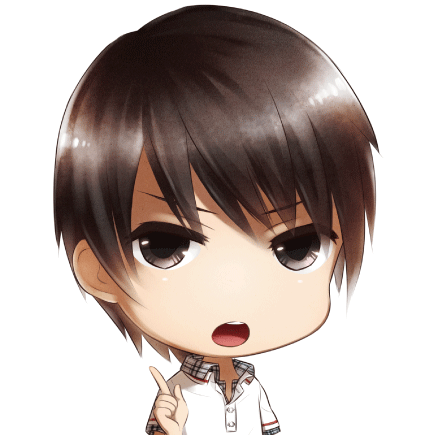 芳樹
芳樹『メルマガ(メールマガジン)』は不要になったら、簡単に登録を解除できます。
あなたにとって損なことは何もありませんよね。
今すぐ、真実の情報を受け取ってください。
裏情報・最新情報を無料で入手しましょう
メールアドレスを入力後、登録ボタンをクリック、次に送信ボタンをクリックで登録完了です。
解除される時は、解除ボタンを2回クリックするだけで簡単に解除できます。